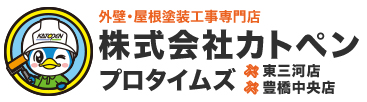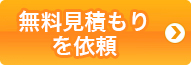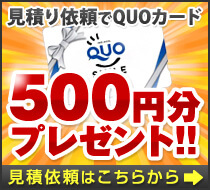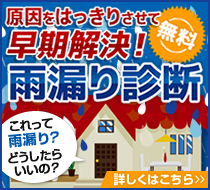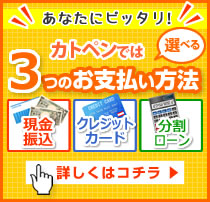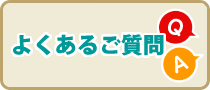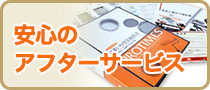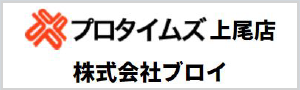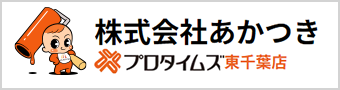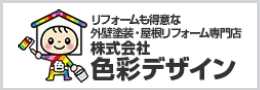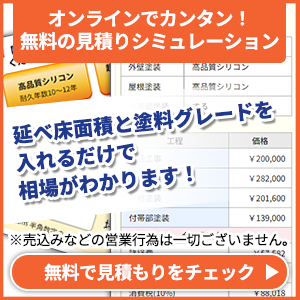- HOME >
- お役立ちコラム
1341件
DATE 2026年2月22日(日)

外壁塗装・屋根塗装はカトペンへ!
お役立ちコラムをご覧いただきありがとうございます。
豊橋市・豊川市で地域密着の優良塗装業者、
屋根・外壁塗装工事はお任せください!
外装劣化診断士の小黒です!
外壁塗装を検討している方の中には「屋根も一緒にやるべきか」との悩みを持っているケースがあります。一度に済ませれば足場代が浮くと分かっていても、数十万円単位でかかるため、ためらう方も少なくありません。
実は近年、賢くメンテナンスを行う世帯の多くが「同時施工」を選択しています。費用を抑えられるのはもちろん、その他にも理由があるのです。今回のお役立ちブログでは、プロの視点から同時施工のメリットや落とし穴などを見極めるための判断軸を中心にお話しします。
▼合わせて読みたい▼
豊川市で屋根塗装・修理を考える前に|工事が必要な劣化サイン
同時施工のメリット

はじめに、外壁と屋根を同時塗装するメリットについて見てみましょう。
足場費用(15〜25万円)を1回に集約できる
同時施工を選ぶ最大の経済的メリットは、「足場代」の重複をなくせることです。一般的な延床面積30坪程度の2階建て住宅の場合、足場の設置・解体には1回あたり15〜25万円の費用がかかります。職人の人件費や足場材の運搬費、保険料などが含まれます。
- 別々に工事した場合:足場代(20万円)×2回=計40万円
- 同時に工事した場合:足場代(20万円)×1回=計20万円
これらのように、同時施工にするだけで節約ができます。
メンテナンス周期を統一し、将来の修繕計画をシンプルにできる
住宅のメンテナンスは一度行えば完了ではありません。10~20年のスパンで繰り返されるものです。外壁と屋根を別々のタイミングで工事してしまうと、数年おきに「次はどこを修繕すべきか」という管理の手間が発生し続け、家計の管理が非常に複雑になります。
同時施工で時期を揃えてしまえば、「わが家のメンテナンスは15年おき」というように、将来の支出時期が予測しやすいでしょう。
近隣への挨拶や工事中のストレスを最小限の期間に凝縮できる
まず、工事が決まると「騒音や振動・塗装特有の臭い・職人の車両通行」などについて、近隣住民への配慮は欠かせません。次に、工事期間中の「生活の制限」がもたらすストレスです。足場が組まれると、家全体が養生ネットで覆われるため、室内は日中でも薄暗くなります。
窓を開けての換気が制限されるだけでなく、プライバシーの観点からも常にカーテンを閉め切った生活になるでしょう。外壁と屋根の塗装を同時に行えば、これらのストレスを最短2~3週間程度の1回に凝縮できます。
▼合わせて読みたい▼
外壁塗装の費用はどう決まる?高い・安いの判断基準を解説
セット検討時に注意すべき「家計」と「劣化」のギャップ

外壁と屋根塗装をセットで依頼する際、ギャップに見舞われて想定外のことが起こるケースも少なくありません。何が起こってしまうか見てみましょう。
短期的な「支払い総額」の増大とキャッシュフローの検討
最大のデメリットは、一度に出ていくお金が大きくなることです。外壁塗装単体であれば100万円前後で収まっても、屋根のカバー工法や補修を合わせると150~250万円ほどに跳ね上がることがあります。将来的に20万円得をすると理解していても、今現在のキャッシュフローが不足している場合、無理な同時施工は日々の生活を圧迫しかねません。
屋根と外壁で「劣化スピード」が異なる場合の判断の難しさ
同時施工すべきかの判断が難しい理由は、外壁と屋根が同時に傷むわけではないからです。日当たりが強烈な立地では屋根の塗装が先にボロボロになる一方で、壁はまだきれいな状態を保っていることもあります。
きれいな部分に手を加えるのはもったいないと感じる方もいますが、大切なのは部分的な美しさではなく足場の効率です。壁がまだきれいでも、5年後に壁のメンテナンスが必要になるのであれば、今一緒にやってしまった方がトータルコストは確実に安くなります。
予算を優先するあまり、塗料のグレードを妥協するリスク
屋根と外壁を一緒に依頼したい方に陥る罠が「両方のグレードを均等に下げる」という選択です。たとえば、本当は15年持つフッ素塗料を使いたいのに、予算のために10年しか持たない安価な塗料にグレードを落としてセット施工をするのは、最悪の選択になりかねません。なぜなら、耐用年数が短い塗料を選ぶと外壁塗装の間隔が縮まるためです。
予算が厳しい場合は、中途半端に済ませるのではなく、今回は屋根だけを最高級の仕様で実施し、外壁は足場なしで可能な範囲で補修するといった形で、優先順位を明確にすることが大切です。
▼合わせて読みたい▼
外壁塗装の見積もり完全ガイド|費用相場と比較ポイントを解説
同時にやるべきか、別々でいいかを見極める「3つの判断軸」

迷っているあなたのために、プロが現場で行っている客観的な3つのチェックポイントをお話しします。判断軸に照らし合わせることで、外壁塗装の最適なタイミングが見えてきます。
築年数と「足場が必要な付帯部」の劣化状況を確認する
外壁塗装を検討する際、どうしても壁の汚れやひび割れに目が向きがちですが、同じくらい重要なのが「付帯部」の劣化です。雨樋の歪みや変色、屋根の裏側にある軒天(のきてん)の剥がれ、破風板(はふいた)の塗膜剥離などが挙げられます。高所にあるため、普段は気づきにくいのが難点です。
最大のポイントは、これらの補修には必ず「足場」が必要になることです。もし今回、予算を削って外壁だけを塗装し、数年後に「雨樋が壊れた」となれば、その修理のためだけに再び足場代がかかってしまいます。個別の不具合をその都度追いかけるのではなく、「足場があるこの機会に、高所のメンテナンスを全て終わらせる判断こそが、費用を抑える賢い選択と言えるでしょう。
次回の塗り替え時期を明確にする
「今回の工事を人生最後の大きな修繕にしたいのか」「数回はメンテナンスを行う予定か」で選択は変わります。仮に、10年後に家全体を見直す予定であれば、予算を抑えて劣化が激しい部位だけを先行させても良いでしょう。
しかし、今後20年は何もしたくないと考えるのであれば、屋根と外壁の両方に高耐久な無機塗料などを用いて、同時に工事を完了させるべきです。重要なのは屋根と外壁の耐久性を合わせることです。一方が早く傷んでしまう組み合わせを避けることが、同時施工のメリットを最大限に引き出す秘訣になります。
一方に「今すぐ直すべき緊急のサイン」が出ていないか確認する
屋根に雨漏りが発生していたり、外壁に深いひび割れや雨染みが見られたりする場合、放置すれば柱や土台といった構造部まで腐食し、修繕費用が数百万円単位で膨れ上がるリスクがあります。
もし緊急性の高いサインが出ている場合、たとえ片方の劣化があまり見られなくても、足場を組む機会に一気に直してしまうのが賢明です。
FAQ|外壁と屋根の同時工事についてよくある質問

外壁と屋根の同時メンテナンスを検討される際、多くの方が疑問に感じるポイントをまとめました。失敗しないための事前知識としてお役立てください。
Q.屋根と外壁で使う塗料の耐用年数は同じにするべきですか?
A.次回の工事時期を合わせるために、耐用年数は揃えるのが基本です。
屋根は外壁よりも直射日光や雨風のダメージを直接受けやすいため、同じグレードの塗料を塗ると屋根の方が早く劣化してしまいます。そのため、屋根には外壁よりもワンランク上の高耐久な塗料(外壁がシリコン塗料なら屋根はフッ素塗料など)を選ぶことをおすすめします。
耐久年数を調整して合わせることで、次回メンテナンスも再び足場代を節約して同時に行うことが可能になります。
Q.同時工事の期間はどのくらいかかりますか?
A.天候や建物の大きさにもよりますが、およそ2〜3週間が目安となります。
外壁単独の塗装工事が10日〜2週間程度であるのに対し、屋根の洗浄や下地処理、塗装の工程が追加される分、数日から1週間ほど工期が延びます。悪天候が続くと作業できない日が発生するため、スケジュールには余裕を持たせておくことが大切です。
ただ、別々に足場を2回組むより、トータルの工期と生活制限のストレスは大幅に短縮できます。
Q.予算が足りない場合、外壁と屋根のどちらを優先すべきですか?
A.劣化状況によりますが、基本的には建物を守る要である「屋根」を優先すべきです。
屋根の劣化や雨漏りは、建物の構造部を直接腐食させる原因になり、家全体の寿命を縮めてしまうためです。外壁の傷みが軽微であれば、今回は屋根のみを高耐久な仕様でしっかり施工し、外壁は見送るという判断も有効です。
ただし、外壁に深いひび割れがあり、すでに雨水が浸入しているような緊急事態であれば早急な同時対処が必要です。
Q.近隣への挨拶は工事の何日前に済ませるべきですか?
A.トラブルを防ぐため、工事着工の1週間前までには済ませておくのが理想です。
足場の組み立て時や高圧洗浄時は、金属音などの大きな音や水しぶきの飛散が発生します。事前に工事期間や作業内容を記した書面をお渡しし、直接ご挨拶しておくことで、近隣住民の方々の不安やストレスを和らげることができます。
Q.同時工事でリフォームローンを活用することは可能ですか?
A.多くのケースでリフォームローンの活用が可能です。
同時工事で一時的な支払い総額が大きくなる場合、手元に現金を残しつつ月々の負担を抑えるためにローンを利用される方は少なくありません。
金利や審査の条件は金融機関によって異なるため、契約前に無理のない支払いシミュレーションを確認しておくことが重要です。
外壁と屋根の同時工事で費用を抑える!最適な時期の診断は「カトペン」へ

外壁と屋根の同時工事は、数十万円かかる足場代を節約し、将来の修繕計画をシンプルにする非常に合理的な選択です。しかし、目先の費用削減だけにとらわれて塗料のグレードを妥協したり、建物の実際の劣化状況と合わないプランを選んだりすると、結果的に生涯のメンテナンスコストが高くついてしまうリスクも潜んでいます。
大切なのは、ご自宅の現在の状態を正確に見極め、今本当に同時施工すべきタイミングなのかを客観的に判断することです。屋根と外壁の劣化スピードの違いや、高所にある雨樋・破風板などの付帯部の傷み具合は、ご自身ではなかなか確認が難しい部分です。特に屋根の上は普段見えないため、雨漏りなどの深刻な事態になってから気づくケースが後を絶ちません。
少しでもお住まいのメンテナンス時期や予算配分に迷われたら、ぜひ株式会社カトペン/プロタイムズ東三河店/豊橋中央店にご相談ください。カトペンでは、お客様の現在の家計の状況や将来のライフプランに寄り添い、本当に必要な工事だけを適正価格でご提案いたします。専門知識を持ったプロが徹底的に診断を行い、無理な同時工事を押し付けるようなことは決してありませんのでご安心ください。
大切なお住まいを長く美しく守るための最適なプランを、カトペンが全力でサポートいたします。ご相談は、24時間受付の問い合わせフォームからのお問い合わせをはじめ、詳細をお伝えいただけるメール、専門スタッフに直接相談できる電話でのご相談、実際の塗料サンプルを見て検討できるショールームへの来店をご用意しております。ご都合に合わせた窓口から、いつでもお気軽にご連絡ください。
▼合わせてチェックしたい▼
DATE 2026年2月18日(水)

外壁塗装・屋根塗装はカトペンへ!
お役立ちコラムをご覧いただきありがとうございます。
豊橋市・豊川市で地域密着の優良塗装業者、
屋根・外壁塗装工事はお任せください!
外装劣化診断士の小黒です!
業者から「今すぐ必要」と言われても「本当に今必要か」と疑うのは当然の反応です。すべての家に即工事が必要なわけではありません。しかし、判断を誤って放置しすぎると、将来の修繕費が3倍に跳ね上がるリスクも潜んでいます。
修繕費を抑えるには、早めの対処が大切です。今回のお役立ちコラムでは、プロの視点から「様子見でOKな家」と「放置厳禁なSOSサイン」の境界線をお話しします。
▼合わせて読みたい▼
豊橋市で外壁塗装を考え始めたら最初に知るべき3つの判断軸
結論:すべてのお家に「今すぐの工事」が必要なわけではありません

「10年おきにメンテナンス」と言ってくる業者もありますが、目安に過ぎません。車のオイル交換と同じで、立地条件や建材の種類によって最適な時期は前後します。
「営業トーク」に惑わされる前に知っておきたいこと
多くの訪問販売業者が「今すぐ」を強調するのは、お家の劣化を心配しているからではなく、自社の成約ノルマや効率を優先しているケースが少なくありません。塗装の本来の目的は「美観」と「防水」です。
美観が少し損なわれていても、防水機能が維持されていれば、建物が急激に腐食することはありません。業者の言葉を鵜呑みにせず、「防水性能が機能しているか」を基準に考えましょう。
見た目が綺麗でも「中」が傷んでいる場合は要注意
外壁の健康状態は、パッと見の印象だけでは決まりません。色あせは少ないものの、サイディングの継ぎ目が割れ、雨水が内部へ浸入している場合は、「汚れ」と「構造的な傷み」を切り分けて考えることが大切です。
▼合わせて読みたい▼
外壁塗装で後悔する人が必ず見落とす診断前チェック
【様子見でOK】まだ外壁塗装をしなくていい家の特徴
次の条件に当てはまる場合、「まだ早い」と判断して良いでしょう。
築年数が浅く防水機能が維持されている
よほど過酷な環境でない限り、外壁の防水機能は十分に機能しています。最近のサイディングボードは工場出荷時の塗装が優秀で、10年以上持つことも珍しくありません。
汚れや苔はあるが、ひび割れや粉吹きは見られない
北側の壁に苔が生えていたり、雨筋の黒ずみが目立ったりすると不安になりますよね。しかし、苔や汚れは、塗膜の防水性が低下し、壁が湿気を含みやすくなっているサインです。
ただし、壁自体が反ったり割れたりしていなければ、今すぐ雨漏りするわけではありません。「美観」を気にしないのであれば、洗浄のみで様子を見るという選択肢もありますが、防水機能は落ち始めていると認識しておきましょう。
色あせが限定的で、外壁材自体に反りや浮きがない
多少の色あせがあっても、外壁材(ボード)そのものが変形していなければセーフです。ボードが平らで、壁にしっかり密着しているなら、保護機能は保たれています。外壁材が水分を吸って「反り」や「浮き」が出る前であれば、数年程度の猶予はあります。
【放置は危険】先延ばしが将来の修繕費を跳ね上げるサイン

「まだ早い」と信じたい気持ちは分かりますが、次のサインが出ている場合は要注意です。
幅0.3mm以上のひび割れ(構造クラック)が発生している
髪の毛ほどの細いひび(ヘアクラック)であれば、次のシーズンまで待っても大きな問題はありません。しかし、幅0.3mm以上(名刺がスッと入る程度)の深いひび割れは危険です。浸入した水は、壁内部の柱を腐らせたりシロアリを呼び寄せたりします。
シーリング(目地)が剥がれ、隙間から下地が見えている
サイディング壁のつなぎ目にあるゴム状の「シーリング」です。ここが割れたりスキマが空いたりしているのは、家に「穴」が開いているのと同じです。塗装の膜が頑丈でも、スキマから水が入れば意味がありません。この場合は部分的な補修や、全体的なメンテナンスを急ぐべきタイミングです。
壁を触ると手が白くなる(チョーキング現象)は「防水ゼロ」の合図
壁を指でスッと撫でた際、白い粉がついたら「チョーキング現象」の可能性が高いでしょう。塗料が紫外線で分解され、バリア機能が消滅しているサインです。雨が降るたびに外壁が水を吸い込み、素材自体の劣化を早めてしまいます。
なぜ業者は「今すぐ」と急かすのか?営業トークの裏側
家の劣化がそれほど深刻に見えなくても、多くの業者は口を揃えて「今すぐ」と決断を急がせます。なぜ、あなたのペースを無視してまで契約を急ぐのでしょうか。「営業トーク」の裏に隠された、業界特有の事情をお伝えします。
「足場代無料」や「期間限定」という言葉の意図
「近くで工事をしているから足場代を無料にする」という提案は、一見するとお得に見えます。しかし、足場代をゼロにしたら業者は儲けが減ります。甘い言葉が並んでいても、業者は利益を残すために他の項目に上乗せしたり必要な工程を省いていたりする可能性が高いでしょう。
放置によるリスクを誇大に伝えていないかを見極める方法
「明日にも雨漏りしますよ」と脅す業者がいたら「あと何か月放置すると、どのような損害が出る予測ですか」と聞いてみましょう。誠実な業者は「雨漏りはないものの、2年放置するとボードが反り、塗装では直せなくなるリスクがある」といった形で、根拠のある説明をしてくれます。
判断を先送りする際に知っておくべきリスク

「今回は外壁塗装を見送る」という選択は、あり得ます。しかし放置すると、次のことが起こるかもしれません。
放置すると塗装では対処できなくなる
外壁メンテナンスは、外壁材が元気なうちであれば「塗装」だけで済みます。しかし、ひび割れや反りを放置して手遅れになると、外壁材そのものを交換する「張り替え工事」が必要になります。
張り替え工事は、古い外壁の撤去費用や新しい建材費がかかるため、塗装費用の2〜3倍に膨れ上がることも珍しくないでしょう。「節約のつもりが高くついた」という事態だけは避けなければなりません。
外壁材そのものが水を吸うと、次の塗料が剥がれやすくなる
外壁材の表面が劣化して水を吸い込むようになると、素材自体がもろくなります。その状態で数年後にいざ塗装をしようとしても、塗料がうまく密着せず、せっかく塗っても数年で剥がれてしまうリスクが高まります。
高級な塗料を使っても、下地(土台)がボロボロでは意味がありません。「いつかやるなら、土台が健康なうちに」済ませるのが、コストパフォーマンスの良い選択です。
建物診断前の相談に来店しませんか?|予約制相談会

「いきなり診断や見積もりはちょっと構える」「本当に塗装が必要かだけ先に整理したい」そんな方ほど、建物診断の前に一度、予約制の相談会で状況を言語化しておくのがおすすめです。
外壁塗装は“やる・やらない”の前に、劣化の種類と緊急度を整理しないと判断がブレます。現地で何を見れば良いのか、診断でどこまで確認すべきか、見積書のどの項目が将来の修繕費に直結するのか。
こうした「判断の分かれ目」を先に押さえておくことで、訪問営業の“今すぐ”に流されず、必要なタイミングで必要な工事だけを選べるようになります。
相談会で整理できること|診断の前に判断軸を作る
相談会では、外壁塗装を急ぐべきかを決めるための“基準”を先に作ります。
たとえば、ひび割れがヘアクラックなのか構造クラック寄りなのか、目地の劣化が部分補修で済む段階か打ち替えを視野に入れる段階か、チョーキングが出ているなら「塗装の話」ではなく「下地の寿命の話」になっていないか。写真(スマホでOK)や築年数、外壁材、過去のメンテ歴、気になる症状をもとに、何を優先して確認すべきかを整理します。
結果として、診断を依頼する場合でも「どこを見る診断なのか」が明確になり、見積もり比較の精度が一気に上がります。
予約方法は公式LINEから|希望日を送るだけでOK
相談会は予約制です。ご予約は公式LINEの追加から進めてください。
LINE追加後に、
①お名前(任意)
②希望日時(第1〜第3希望)
③相談したい内容(例:目地の割れ、ひび割れ、チョーキング、訪問業者に急かされた等)
④可能なら外壁の写真
上記を送っていただければOKです。こちらで空き枠を確認し、折り返しご案内します。
「診断を受ける前に、まず話だけ聞きたい」という段階でも問題ありません。判断を急がず、根拠を持って“先延ばししていい家かどうか”を一緒に整理しましょう。
FAQ|外壁塗装の先延ばしについてよくある質問

外壁塗装を急ぐべきか迷う方が特に引っかかりやすい論点を、判断軸がブレないように整理しました。
Q.築10年を超えたら必ず塗装が必要?
A.必ずではありません。
年数は目安で、優先すべきは防水の機能低下サイン(目地の割れ・隙間、0.3mm以上のひび、チョーキング、反りや浮き)の有無です。症状が軽ければ洗浄や部分補修で猶予を作れる場合もあります。
Q.チョーキングが出たら「今すぐ」やらないとダメ?
A.放置し続けるのはおすすめしませんが、今日明日で雨漏りするとは限りません。
チョーキングは塗膜の寿命サインなので、次の雨期や台風シーズンまでに「劣化が進みやすい面(南面・西面)」と「目地」の状態を優先確認し、工事時期を逆算すると失敗しにくいです。
Q.0.3mmのひび割れは自分で見分けられる?
A.完全ではないものの目安は作れます。
名刺やクレジットカードの角が“スッ”と入る、雨の後にひび周辺が乾きにくい、ひびが一直線に長く伸びている、こうした場合は深い可能性があります。逆に髪の毛程度の細さで短く点在するなら緊急度は下がります。
Q.目地の割れは塗装だけで直る?
A.割れ方によります。
表面の細かなひび程度なら塗装で保護できることもありますが、隙間が開いて下地が見える、剥離して浮いている、触ると硬化して割れる場合はシーリング補修が前提です。塗装の膜が強くても“入口”が開いていると再発しやすい点が注意です。
Q.「足場代無料」「近くで工事中」は本当にお得?
A.条件次第です。
足場がゼロ円になるほどの原価メリットは通常小さいため、別項目への上乗せや工程の省略がないかを確認しましょう。確認ポイントは次の4点です。
- 下地補修の範囲と単価(ひび・欠け・浮きの扱い)
- シーリングの仕様(増し打ち/打ち替え、材料グレード)
- 塗布量や塗り回数(工程写真や仕様書で確認)
- 保証の対象範囲(何が対象外かまで)
カトペンで「先延ばしOKか」を整理してから相談しませんか?

外壁塗装は「今すぐ」か「まだ先」かの二択ではなく、劣化の種類と進行度で最適解が変わります。
株式会社カトペン/プロタイムズ東三河店/豊橋中央店では、先延ばしできる状態か、先に止血すべきサインが出ているかを、判断軸ベースで整理できるようにお伝えいたします。もし検討を進めるなら、まずは“何を確認してから見積比較すべきか”を押さえたうえで動くのが近道です。
問い合わせフォームからのお問い合わせ、メール、電話でのご相談、ショールームへの来店のいずれでもOKです。訪問販売で急かされた、見積の金額差の理由が分からない、目地とひびのどちらを優先すべきか迷う、など状況を添えていただけると判断が早くなります。
外壁の写真(全景+気になる箇所のアップ)と、希望時期(今季/半年以内/来年以降)だけでも添えていただければ、優先順位の整理がスムーズです。
▼合わせてチェックしたい▼
DATE 2026年2月15日(日)

外壁塗装・屋根塗装はカトペンへ!
お役立ちコラムをご覧いただきありがとうございます。
豊橋市・豊川市で地域密着の優良塗装業者、
屋根・外壁塗装工事はお任せください!
外装劣化診断士の小黒です!
外壁塗装の検討を始めて直面するのが「価格の不透明さ」です。
- 同じ作業なのに、業者によって金額差が出る理由って何?
- 安いに越したことはないけれど、安すぎると手抜きが怖い
- 高くても高品質とは限らない
これらの戸惑いを感じるのは、あなたが真剣に業者を見極めようとしている証拠です。費用が決まる際には基準があります。今回のお役立ちコラムでは「外壁塗装の費用は何によって決まるのか」「値段をどう判断すべきか」などをお話しします。
▼合わせて読みたい▼
「外壁塗装の見積もり完全ガイド|費用相場と比較ポイントを解説」
見積金額に「大きな差」が出る理由

塗装業界は、家電製品や自動車のような「定価」がありません。提示される金額に数十万円の差が出るのは、次の理由があるからです。
①「見えない工程」への手間のかけ方
塗装の寿命の8割は、塗る前の「下地処理」で決まります。古い塗膜を剥がし、ひび割れを埋め、サビを落とす。地味で手間のかかる工程にどれだけ職人の時間を割くかで、見積金額は変わります。丁寧にやる会社は人件費が高くなり、パッと見の綺麗さだけを求める会社は、工程を削ることで安さを実現します。
②塗料の「缶数」と「乾燥時間」のルール
塗料にはメーカーが指定した「平米あたりに使う量(塗布量)」と、次の工程までの「乾燥時間」が厳格に定められています。安く上げるために塗料を薄めたり、3回塗るべきところを2回に減らしたりすれば、材料費と人件費の両方を削れます。しかし「本来の性能を発揮できない塗装」を売っていることに他なりません。
③会社の「運営構造」による中間マージン
大手ハウスメーカーやリフォーム仲介会社を通すと、工事を行う下請け会社との間に中間マージン(紹介料や管理料)が発生します。「ブランドの安心感」という付加価値はありますが、自社職人による直接施工の会社であれば、同じ金額でも「現場の材料や手間」により多くの予算を投入できるため、実質的な工事の質が高くなる傾向にあります。
▼合わせて読みたい▼
外壁塗装に必須?相見積りのメリットとデメリットについて
他者よりも大幅に安い場合はリスクが潜んでいることがある!
「見積もりが他社より圧倒的に安い」場合、リスクが潜んでいることもあります。理由を見てみましょう。
「下地調整」の簡略化という罠
塗装において、最もコストカットしやすいのが下地調整です。高圧洗浄を短時間で済ませたり、下地の補修を「上から塗れば隠れる」と省略したりすれば、短期的には綺麗に見えます。しかし、土台が整っていない塗装は、数年で「ベロリと剥がれる」「内側から腐食する」といった致命的な不具合を招きます。
人件費の削りすぎが招く「施工不良」
相場を大きく下回る受注は、現場の職人に「1日でも早く終わらせろ」というプレッシャーを与えます。結果、冬場や湿度の高い日に無理に塗装を強行したり、塗料が乾ききる前に次の層を塗ってしまったりといった、マニュアル無視の施工が起きやすくなります。これらは、塗膜の寿命を決定的に縮めるでしょう。
「生涯コスト」で見ると高くなる場合も
工事費が安かったとしても、本来15年持つはずの塗装が5年でダメになれば、10年後にはまた100万円単位の出費が必要になります。安さ重視の選択は、実は「最もメンテナンスサイクルを早め、生涯で払う住居費を最大化させる選択」になりかねないのです。
▼合わせて読みたい▼
外壁塗装でよくある後悔例|安さだけで選ぶと起きること
プロが教える「高い・安い」を判断する3つの物差し

値段を判断する際は、次の3つのことをベースに判断すると良いでしょう。
①「1年あたりのコスト」で比較する
支払額の総額だけで比較するのではなく、塗装が「何年持つか(期待耐用年数)」で割った、年間コストで考えることが大切です。2つのプランを例に見てみましょう。
| 項目 | プランA(一般塗料) | プランB(高耐候塗料) |
| 初期費用 | 100万円 | 130万円 |
| 期待耐用年数 | 10年 | 20年 |
| 年間コスト | 10万円/年 | 6.5万円/年 |
| 30年間の実質コスト | 300万円(3回分) | 195万円(1.5回分) |
プランBの方が初期投資額は30万円高いものの、30年間のランニングコストを見ると割安です。目先の支払い額よりも、長期的なコストパフォーマンス(ライフサイクルコスト)を重視するのが賢い選択です。
②診断の「緻密さ」をチェックする
見積金額の根拠となる「塗装面積」がどう算出されたかを確認しましょう。お家の坪数から出した見積もりと、図面や実測に基づき、窓などの塗らない部分を除いた「正味の平米数」を出した見積もりでは、信頼度が全く違います。
③「安心の対価」が含まれているか見る
塗装は「完成品」を買うのではなく、現場で作られる「サービス」を買うものです。万が一の不具合に対応する保証制度や、数年ごとの定期点検の費用、あるいは何かあった際にすぐ駆けつけてくれる地域密着の体制が挙げられます。それらの「安心の対価」が含まれているのであれば、多少の金額差は「保険料」として妥当なものと考えられます。
▼合わせて読みたい▼
外壁塗装の保証は何年が正解?5年・10年・15年の違いと失敗しない選び方
費用を抑えつつ質を担保するためのポイント

「予算に限りはあるが、手抜き工事はされたくない」「質は落とさず、賢くコストを下げたい」という方のために、プロが教える健全なコストダウンの方法をお話しします。
「自社施工」の会社を候補に入れる
ハウスメーカーや大手リフォーム会社に依頼すると、工事自体は下請け業者に任せることが一般的です。その際、紹介料として「中間マージン」が発生し、費用が割高になります。一方、自社の職人を抱える「自社施工店」であれば、中間マージンをカットできます。
補助金や助成金・火災保険の活用を調べる
自治体によっては、省エネ効果のある「遮熱塗料」の使用や、景観形成に関わる改修に対して数万〜十数万円の補助金が出る場合もあります。また、台風や雪による雨樋の破損など、自然災害が原因であれば「火災保険」が適用できるケースもあるでしょう。ただし、経年劣化による補修には適用されません。
▼合わせて読みたい▼
外壁塗装は補助金終了後いつやるべき?費用を損しない最適タイミングを解説
「閑散期」の施工を相談してみる
塗装業界には繁忙期(春・秋)と閑散期(夏・冬)があります。「夏は塗料が乾きすぎる」「冬は乾かない」といった懸念を持たれがちですが、現在は塗料の性能が向上しており、プロが適切な乾燥時間を守れば品質に問題はありません。時期だけで判断せず「質」や「長期コスト」を含めて比較検討することが、後悔しない外壁塗装への第一歩です。
▼合わせて読みたい▼
外壁塗装の予約はいつがベスト?季節ごとのメリット・デメリットと失敗しない時期選び
FAQ|外壁塗装の費用判断についてよくある質問

外壁塗装の費用は、金額だけを見ると判断を誤りやすい分野です。ここでは「高い・安い」をどう考えるべきかという点について、実際によく寄せられる質問を整理します。
Q.相見積もりで一番安い業者を選ぶのは間違いですか?
A.必ずしも間違いではありませんが、安い理由を説明できない場合は注意が必要です。下地処理や塗布量、乾燥時間など、削りやすい工程が省かれていないかを確認せずに選ぶと、数年後に再塗装が必要になるリスクがあります。価格だけでなく、内容と根拠をセットで見ることが重要です。
Q.高い見積もり=良い工事と考えていいのでしょうか?
A.金額が高いだけで、工事の質が保証されるわけではありません。重要なのは「何に費用が使われているか」です。塗料の性能、下地処理の工程数、保証や点検体制などが明確であれば、価格差に納得しやすくなります。説明が曖昧な高額見積もりは慎重に判断すべきです。
Q.見積書のどこを見れば、適正価格か判断できますか?
A.塗装面積の算出方法と、工程ごとの内訳を見ることがポイントです。「一式」表記が多い見積書よりも、実測に基づいた平米数と工程が分かれている見積書の方が、費用の妥当性を判断しやすくなります。
カトペンと考える|外壁塗装の費用で後悔しないための相談窓口

外壁塗装の費用は「安いか高いか」ではなく「その金額で何が得られるのか」を基準に考える必要があります。目先の支払額だけで判断すると、数年後に再工事が必要になり、結果的に住まいの生涯コストが高くなるケースも少なくありません。
本当に大切なのは、下地処理や塗布量といった見えない工程が適切に組み込まれているか、耐用年数を踏まえたコストパフォーマンスになっているか、そして万が一の際に相談できる体制があるかどうかです。これらを整理して初めて「高い・安い」を冷静に判断できるようになります。
株式会社カトペン/プロタイムズ東三河店/豊橋中央店では、見積金額の大小だけで良し悪しを決めるのではなく、なぜその費用になるのか、長期的に見て納得できる選択かを一緒に整理することを重視しています。今すぐ工事を決める必要はありません。迷っている段階だからこそ、第三者視点で整理する価値があります。
外壁塗装の費用について不安や疑問がある方は、問い合わせフォームからのお問い合わせ、メールでのご相談、電話でのご相談、ショールームへの来店など、ご都合のよい方法でカトペンにご相談ください。カトペンは、金額に振り回されず、納得して判断できる外壁塗装をサポートします。
▼合わせてチェックしたい▼
DATE 2026年2月11日(水)

外壁塗装・屋根塗装はカトペンへ!
お役立ちコラムをご覧いただきありがとうございます。
豊橋市・豊川市で地域密着の優良塗装業者、
屋根・外壁塗装工事はお任せください!
外装劣化診断士の小黒です!
豊橋市で外壁塗装を考え始めると、まず相場や業者の評判を調べたくなります。
しかし、情報を集めれば集めるほど判断が難しくなり「結局どう決めればいいのか分からない」という状態に陥りがちです。
外壁塗装は、価格やランキングを見てから決める工事ではありません。判断の順番を誤ると、後から後悔につながる可能性があります。重要なのは、最初に“どんな基準で判断するか”を整理することです。
今回のお役立ちコラムでは「豊橋市で外壁塗装を判断する際に、最初に整理すべき3つの判断軸」について解説します。
▼合わせて読みたい▼
豊橋・豊川で外壁塗装業者を選ぶなら?口コミより確かな見極め方
なぜ外壁塗装は「判断軸」を持たずに進めると失敗しやすいのか

外壁塗装で後悔が生まれやすいのは、判断に必要な軸が定まらないまま情報収集を始めてしまうからです。判断軸がない状態では、どれだけ情報を集めても比較が成立せず、決断の根拠を持てません。ここでは、なぜ判断軸を持たずに進めると失敗しやすいのか、その構造を整理します。
相場・口コミから見始めてしまう判断ミス
外壁塗装を検討する際、多くの人が最初に相場や口コミを調べます。
しかし、この順番が判断を難しくする原因になります。相場は条件によって大きく変わるため、基準を持たずに見ると「高い」「安い」という印象だけが残ります。口コミも、評価の良し悪しは分かっても、自分の家に当てはまるかどうかは判断できません。
本来は、何を重視して外壁塗装を行うのかを決めてから、相場や口コミを見る必要があります。順番を誤ると、情報に振り回される状態になります。
「なんとなく今やるべき」で決めてしまう危険性
「そろそろ時期だから」「営業で言われたから」といった理由で判断してしまうケースも少なくありません。この判断には明確な根拠がなく、後から「本当に今必要だったのか」と迷いが生じやすくなります。
判断軸がないまま進めると、急ぐ必要のない工事をしてしまったり、逆に必要な対応を先延ばしにしたりするリスクが高まります。
判断軸がないと比較が成立しない
見積を複数取っても決めきれない理由は、比較の基準が曖昧だからです。
価格、工事内容、提案内容をどう評価すればよいかが整理されていないと、どの見積にも一長一短が見えてしまいます。その結果「どれも決め手に欠ける」という状態になり、判断が止まります。
判断軸を先に持っていれば、情報を整理しながら比較でき、後悔しにくい選択につながります。
▼合わせて読みたい▼
外壁塗装に必須?相見積りのメリットとデメリットについて
豊橋市で外壁塗装を判断するための3つの軸

外壁塗装の判断は、感覚や周囲の意見で決めるものではありません。
豊橋市の住宅事情を踏まえると、判断は大きく「価格」「時期」「劣化状況」の3つの軸で整理できます。この3軸を同時に確認することで、判断がブレにくくなり、後悔の可能性を下げることができます。
判断軸①:価格で判断してよいケース・危険なケース
価格は判断材料の一つですが、軸そのものにしてしまうと失敗しやすくなります。
「安いから」「高いから」という理由だけで判断すると、必要な工程が省かれていたり、過剰な仕様になっていたりする可能性があります。一方で、条件が揃っており、工事内容も理解できている場合には、価格を比較材料として使うことは有効です。
重要なのは、価格を先に見るのではなく、内容を理解したあとに価格を確認する順番を守ることです。価格は結果であって、判断の出発点ではありません。
判断軸②:時期で判断すべきケース・待てるケース
外壁塗装の時期は、住宅の状態と地域条件によって判断が分かれます。劣化が進んでいる場合や、雨水侵入のリスクが高い状態であれば、時期を理由に先延ばしにすることは適切ではありません。
一方で、劣化が軽微で緊急性が低い場合は、気候が安定する時期や繁忙期を避けて計画する判断も成立します。時期判断は「今やるか、待つか」の二択ではなく、状態と環境を踏まえた選択であることを理解する必要があります。
判断軸③:劣化状況を基準にするという考え方
最も優先すべき判断軸が、外壁の劣化状況です。見た目のきれいさだけでなく、防水性能や保護機能が維持されているかを基準に考える必要があります。ひび割れ、塗膜の剥がれ、チョーキングなどは、機能低下のサインです。
劣化状況を基準にすれば「今やるべきか」「まだ待てるか」の判断が整理しやすくなり、価格や時期の判断も自然に噛み合ってきます。
▼合わせて読みたい▼
外壁塗装の予約はいつがベスト?季節ごとのメリット・デメリットと失敗しない時期選び
判断に迷ったときに取るべき次の行動

3つの判断軸で整理しても、すべてのケースで即答が出るわけではありません。むしろ、判断に迷う状態は自然であり、無理に結論を出す必要はありません。
重要なのは、迷ったときにどの行動を選ぶかです。
ここでは、判断を誤らないために取るべき次の行動を整理します。
「まだ決めない」という判断も一つの選択
外壁塗装は高額で、やり直しが難しい工事です。そのため、納得できないまま契約するよりも「まだ決めない」という判断が合理的な場合もあります。価格・時期・劣化状況のいずれかに不確実性が残る場合は、判断を保留すること自体がリスク回避になります。
重要なのは、先延ばしを感覚で行うのではなく「何が分かっていないのか」を明確にしたうえで保留する姿勢です。
状態を把握するための診断という選択肢
判断に迷う最大の原因は、外壁の状態が把握できていないことです。診断は、必ずしも工事を前提とする行為ではありません。
現在の劣化状況や防水性能を確認し「今やるべきか」「待ってもよいか」を判断するための材料を得る行為です。状態を知ることで、判断軸が具体化し、迷いが整理されます。
後悔しないために情報をどう使うか
相場情報や失敗事例は、判断を助けるための材料であり、結論を押し付けるものではありません。重要なのは、それらの情報を「自分の判断軸」と照らし合わせて使うことです。
過去の後悔例を知ることで、同じ判断ミスを避ける視点が持てます。判断に迷ったときは、情報を集める順番と使い方を意識することで、冷静な選択につなが流でしょう。最終的に納得して決められるかどうかが、外壁塗装で後悔しないための分かれ道になります。
▼合わせて読みたい▼
外壁塗装の色選びで失敗しない!豊橋市の気候とトレンドに合うおすすめの色とは?
FAQ|豊橋市で外壁塗装を判断する際によくある質問

外壁塗装は情報量が多く、判断に迷いやすい工事です。ここでは、豊橋市で外壁塗装を検討される方から特によく寄せられる質問を整理し、判断軸をより明確にするための補足としてまとめました。
Q.豊橋市で外壁塗装の相場を先に調べるのは間違いですか?
A.相場を知ること自体は間違いではありませんが、判断の出発点にするのはおすすめできません。外壁塗装の費用は、劣化状況・工事範囲・施工内容によって大きく変わります。判断軸を持たずに相場だけを見ると「高い・安い」という印象だけが残り、適切な比較ができなくなります。まずは状態と目的を整理したうえで、相場情報を参考にすることが重要です。
Q.外壁塗装は築年数だけで判断してもいいのでしょうか?
A.築年数は一つの目安にはなりますが、判断材料としては不十分です。同じ築年数でも、立地環境やこれまでのメンテナンス状況によって劣化の進み方は異なります。築年数よりも、ひび割れ・塗膜の状態・防水性能など、実際の劣化状況を基準に判断する方が後悔につながりにくくなります。
Q.判断に迷った場合、無料診断は受けた方がいいですか?
A.「今やるべきか迷っている段階」こそ、診断は有効な選択肢です。無料診断は必ずしも工事を前提とするものではありません。現在の状態を把握し、価格・時期・劣化状況の判断軸を具体化するための材料として活用できます。営業されることが不安な場合は、判断目的であることを明確にしたうえで相談すると安心です。
カトペンと一緒に考える|豊橋市で外壁塗装を後悔なく判断するために
外壁塗装で後悔が生まれる多くの原因は、価格や評判を先に見てしまい、判断の軸を整理しないまま進めてしまうことにあります。
豊橋市で外壁塗装を検討する際は「価格」「時期」「劣化状況」という3つの判断軸を先に整理することで、情報に振り回されにくくなります。判断に迷うこと自体は、決して悪いことではありません。むしろ、迷っている段階こそが冷静に考えるための重要なタイミングです。
株式会社カトペン/プロタイムズ東三河店/豊橋中央店では、工事を前提に話を進めるのではなく「今やるべきか」「まだ待てるか」「何を基準に判断すべきか」を一緒に整理することを大切にしています。
外壁塗装について不安や迷いがある場合は、判断材料を整理するための一歩として、まずはお気軽にご相談ください。
問い合わせフォームからのお問い合わせ、メールでのご相談、電話でのご相談、ショールームへのご来店など、ご都合に合わせた形でカトペンが対応いたします。最終的に「納得して決められた」と思える判断につながるよう、カトペンが丁寧にサポートします。
▼合わせてチェックしたい▼
DATE 2026年2月8日(日)

外壁塗装・屋根塗装はカトペンへ!
お役立ちコラムをご覧いただきありがとうございます。
豊橋市・豊川市で地域密着の優良塗装業者、
屋根・外壁塗装工事はお任せください!
外装劣化診断士の小黒です!
外壁塗装で後悔したくないと考えたとき、多くの人は「良い業者を選ばなければ」「診断内容を比較しなければ」と思いがちです。
しかし実際には、診断そのものよりも、その前段階での考え方が整理されていないことが原因で迷いが深まるケースが少なくありません。診断を受ける準備ができていないまま話を聞くと、説明の多さや専門用語に圧倒され、判断軸を見失いやすくなります。
重要なのは、不安を減らすために診断を受けるのではなく、判断するために診断を活用できる状態をつくることです。
今回のお役立ちコラムでは「外壁塗装で後悔する人が必ず見落とす診断前チェック」について解説します。
▼合わせて読みたい▼
外壁塗装でよくある後悔例|安さだけで選ぶと起きること
外壁塗装の後悔は「診断の質」ではなく「受ける側の準備」で決まる

外壁塗装の後悔は、診断内容が間違っていたから起きるとは限りません。
むしろ多いのは、診断結果をどう受け止め、どう判断するかの準備が整っていなかったことで起きる迷いです。診断は判断材料を集めるための工程であって、結論を代わりに出してくれるものではありません。
その前提が共有されていないと、診断後に「結局どうすればいいのか分からない」という状態に陥りやすくなります。
診断結果を正しく受け取れない状態とは何か
診断前に目的が整理されていないと、提示された情報の重みづけができません。劣化の説明、工事内容の提案、将来的なリスクなどが一度に示されると、どれが今すぐ必要で、どれが参考情報なのか分からなくなります。
その結果、不安だけが増え、判断を先送りしたり、逆に勢いで決めてしまったりする原因になります。情報を受け取れない状態とは、知識不足ではなく、判断基準がない状態を指します。
比較する前に判断軸がないと起きるズレ
複数の診断を受けても、判断軸が整理されていなければ比較は成立しません。
価格が違う、説明の量が違う、提案内容が違う、といった差だけが目に入り「どれが正しいのか分からない」という迷いが深まります。本来は、自分が何を優先したいのかによって、納得できる選択肢は変わります。
軸がないまま比較すると、選んだ後に「本当にこれで良かったのか」という後悔につながりやすくなります。
説明が増えるほど不安が大きくなる理由
診断で説明される内容が多いほど、不安が解消されるとは限りません。準備ができていない状態では、情報が増えるほど判断の負担も増えます。
専門的な説明や将来のリスクを聞くことで「全部やらなければいけないのではないか」という感覚に陥ることもあります。診断を安心材料にするためには、受ける前に考える順番を整え、必要な情報を選び取れる状態をつくることが欠かせません。
▼合わせて読みたい▼
豊川市の家を塗り替えで美しく!信頼できる塗装業者の見極め方
診断前に必ず整理しておくべきチェック項目

診断を受ける前に必要なのは、専門的な知識を詰め込むことではありません。大切なのは、自分の中で曖昧になっている点を言葉にし、判断の土台を整えておくことです。
これができていないと、どれだけ丁寧な診断を受けても、情報が積み重なるだけで結論に近づきません。ここでは、診断前に整理しておきたい最低限のチェック項目を挙げます。
なぜ外壁塗装を考え始めたのかを言語化する
最初に確認したいのは、外壁塗装を考え始めたきっかけです。
見た目の劣化が気になったのか、雨漏りやひび割れへの不安があるのか、築年数を意識しての判断なのか。
理由が整理されていないまま診断を受けると、提案のどこを重く受け止めるべきか分からなくなります。完璧な言葉でなくても構いませんが「今、何が気になっているのか」を自分なりに整理しておくことで、診断結果の受け取り方が変わります。
費用・範囲・優先順位をぼんやりでも決めておく
診断の場では、さまざまな工事内容や金額が提示されます。そのときに「どこまでなら現実的か」という感覚がまったくないと、すべてが判断不能に見えてしまいます。
正確な予算を決める必要はありませんが、上限の目安や、今回は見送ってもいい範囲を意識しておくことが重要です。すべてを一度に完璧にしようとしない姿勢が、冷静な判断につながります。
診断で何を確認したいかを先に決める
診断では、劣化状況、工事の必要性、将来のリスクなど、多くの情報が提示されます。その中で何を知りたいのかを決めておくと、説明を取捨選択しやすくなります。
今すぐの工事が必要かどうかを知りたいのか、数年先まで見据えた判断材料が欲しいのか。確認したいポイントが明確であれば、診断を判断材料として活用できるようになります。
▼合わせて読みたい▼
豊橋市の住まいを塗り替えで新しく!地域に密着した塗装業者の選び方と最新トレンド
後悔を防ぐために診断前から持っておきたい視点

診断前の準備が整ったら、次に意識したいのは「診断後に何が起きやすいか」を想像しておくことです。外壁塗装は決断までの工程が多く、一度判断を下すと引き返しにくい工事です。だからこそ、結論を急がないための視点を先に持っておくことで、診断結果を冷静に見られるのです。
工事中・工事後に起きやすいトラブルの視点
後悔の原因は、仕上がりそのものよりも、工事中や工事後の出来事にあるケースも少なくありません。ペンキ汚れや近隣への配慮不足、工事期間中の生活ストレスなどは、診断内容とは別の次元で発生します。
事前にこうした点を想定しておくと、診断時に説明を聞く視点が変わり、必要な確認を見落としにくくなります。
見積もりや費用をどう受け止めるかの考え方
診断後に提示される見積もりは、判断の材料の一つに過ぎません。金額の大小だけで良し悪しを決めるのではなく「なぜこの費用になるのか」「どこが変動しやすいのか」を理解することが重要です。
相場感を知ることは安心につながりますが、数字そのものよりも考え方を押さえておくことで、納得感のある判断がしやすくなります。
地域性や無料診断の位置づけを正しく理解する
外壁の劣化状況や工事の考え方は、地域の気候や住宅環境によっても差が出ます。また、無料診断は便利な入口である一方、判断を代行してくれるものではありません。
地域性や診断の位置づけを正しく理解しておくことで、提示された情報を一般論としてではなく、自分の家に当てはめて考えられるようになります。
▼合わせて読みたい▼
【豊川市・外壁塗装】悪徳業者リストの使い方・主な手口を解説
FAQ|外壁塗装の診断前チェックについてよくある質問

外壁塗装の診断は、不安を解消するための場である一方、準備不足のまま受けてしまうと迷いが増える原因にもなります。ここでは「診断前チェック」というテーマに関して、実際によくある疑問を整理します。
Q.診断前に専門知識を勉強しておく必要はありますか?
A.専門的な知識を事前に詰め込む必要はありません。それよりも重要なのは「なぜ外壁塗装を考えているのか」「今いちばん不安に感じている点は何か」を整理しておくことです。判断軸があれば、専門用語が出てきても必要な部分だけを受け取れるようになります。
Q.無料診断は受けたら必ず工事をしなければいけませんか?
A.無料診断は、あくまで状態を確認するための入口です。工事を決める義務はありませんし、診断=即契約ではありません。大切なのは、診断結果をどう判断材料として使うかであり、そのために診断前チェックが役立ちます。
Q.複数社の診断を受けたほうが安心でしょうか?
A.複数社の診断自体が問題なのではなく、比較するための軸があるかどうかが重要です。診断前に優先順位や確認したいポイントを整理しておけば、1社でも十分判断できるケースもあります。軸がないまま複数社を回ると、かえって混乱することもあります。
カトペンと考える|外壁塗装で後悔しないための診断前整理と相談窓口

外壁塗装で後悔する人の多くは、診断の内容そのものではなく「診断をどう受け止め、どう判断したか」でつまずいています。診断は結論を出してくれる場ではなく、判断材料を集める工程です。その前段階で、なぜ外壁塗装を考え始めたのか、どこに不安があるのか、どこまでを優先したいのかを整理しておくことで、診断は初めて意味を持ちます。
株式会社カトペン/プロタイムズ東三河店/豊橋中央店では、診断を受ける前の段階から「今は診断すべきか」「まだ様子を見てよいのか」「判断材料として何を確認すべきか」といった整理を大切にしています。無理に工事を進めるのではなく、迷っている状態そのものを出発点として、一緒に判断軸を整えていくことが、結果的に後悔を防ぐ近道になります。
外壁塗装について少しでも迷いや不安がある場合は、問い合わせフォームからのお問い合わせ、メールでのご相談、電話でのご相談、ショールームへの来店など、ご都合に合わせてカトペンにご相談ください。カトペンは、外壁塗装を「決めさせる」ためではなく、「納得して判断する」ためのサポートを行っています。
▼合わせてチェックしたい▼
DATE 2026年2月4日(水)

外壁塗装・屋根塗装はカトペンへ!
お役立ちコラムをご覧いただきありがとうございます。
豊橋市・豊川市で地域密着の優良塗装業者、
屋根・外壁塗装工事はお任せください!
外装劣化診断士の小黒です!
屋根は毎日目にする場所ではないため、劣化が進んでいても気づきにくく「そろそろ工事が必要かもしれないが、塗装なのか修理なのか判断できない」と感じている方は少なくありません。
雨漏りなどの明確な被害が出ていない段階ほど判断が難しく、不安だけが残りやすいのが屋根工事の特徴です。重要なのは、費用や工事内容を調べる前に、今の屋根にどんな劣化サインが出ているのかを整理することです。
今回のお役立ちコラムでは「豊川市で屋根塗装・修理を考える前に知っておきたい工事が必要な劣化サイン」について解説します。
▼合わせて読みたい▼
屋根や雨樋に緑青が発生した!原因やリスクは?メンテナンスすべき?
屋根工事を考えるべき劣化サインとは

屋根の劣化は、突然深刻な状態になるものではありません。多くの場合、見た目の変化として徐々に現れ、その段階で適切に対処できるかどうかが、その後の工事内容を大きく左右します。
豊川市の住宅では、強い日差しと雨の影響を長年受けることで、屋根表面の保護機能が少しずつ低下していきます。まずは、比較的初期から確認できる劣化サインを把握し、塗装で対応できる可能性がある段階を見極めることが重要です。
屋根の色あせ・ツヤ消失が示すサイン
屋根全体の色が薄くなったり、塗装直後にあったツヤが消えて、くすんだ印象になったりしている場合、塗膜の劣化が始まっているサインです。見た目の変化だけに感じられますが、塗膜は屋根材を紫外線や雨風から守る役割を担っています。
その機能が弱まると、屋根材が直接ダメージを受けやすくなり、劣化の進行速度が上がります。この段階であれば、塗装によって保護機能を回復できる可能性があり、工事判断の一つの目安になります。
コケ・藻・黒ずみが出始めた屋根
屋根表面にコケや藻、黒ずみが見られる場合、それは屋根が水分を保持しやすくなっている状態を示しています。とくに日当たりの悪い面で起きやすく、塗膜の防水性が低下している証拠といえます。
汚れ自体は落とせても、原因となる保護機能の低下を放置すると、屋根材の劣化につながります。この症状が出ている段階は、塗装による保護を検討すべきタイミングです。
ただし、ご自身で屋根に登って汚れを落とすようなことをすると、万が一その作業で怪我を負ってしまっても保険での治療は難しいということを覚えておいてください。高所作業は健康保険の適用外の状況だということを知らないと、後で高額な治療費を支払うことになるかもしれないのです。
軽微なひび割れ・浮きが見える場合
屋根材に細かなひび割れが入っていたり、端部がわずかに浮いて見えたりする状態も注意が必要です。まだ大きな破損ではなくても、劣化が進行し始めている合図になります。軽度な段階であれば補修と塗装で対応できる可能性がありますが、放置すると修理が必要な状態へ進むことがあります。
違和感を覚えた時点で、状態を整理することが判断ミスを防ぎます。
▼合わせて読みたい▼
豊橋市で起こったスレート屋根の反りは対策できる!放置すると危険な理由もお話しします!
放置すると修理が必要になる危険な症状

ここからは、劣化が表面の問題にとどまらず、屋根本来の役割を果たしにくくなっている可能性が高い症状です。この段階まで進むと、塗装だけで状態を戻すことは難しく、部分的な修理や交換を前提に考える必要が出てきます。
見た目の変化がはっきりしている場合もあれば、違和感として現れることもあるため「気のせい」と片付けずに整理しておくことが重要です。
屋根材の割れ・欠け・ズレ
屋根材が割れている、角が欠けている、並びがズレているといった症状は、屋根の防水構造そのものが崩れ始めているサインです。すぐに専門業者に相談することをおすすめします。
スレート屋根では、ひびが線状ではなく面で広がって見えることがあり、瓦屋根では一部だけ高さが合っていない、影の出方が不自然になるといった変化が現れます。小さな割れに見えても、雨水はわずかな隙間から侵入し、下地へ回り込みます。
塗装は表面を保護する工事のため、割れやズレを元に戻すことはできず、この段階では修理を前提に考える必要があります。
棟板金の浮き・釘抜け
屋根の頂部にある棟板金が浮いている、釘が抜けかけているといった状態も、放置すると被害が広がりやすい症状です。強風や台風の影響を受けやすく、浮きが進むことで雨水の侵入口になりやすくなります。
見上げたときに棟のラインが波打って見える、風の日に音がする場合は注意が必要です。塗装で表面を整えても、固定が弱いままでは意味がなく、まずは浮きを止める、固定し直すといった修理対応が優先されます。
室内に出る前兆(天井のシミ・違和感)
天井や壁に薄いシミが出る、クロスが浮く、雨の日だけ室内が湿っぽく感じるといった変化は、屋根で起きた劣化が室内側へ影響し始めている前兆です。まだ雨漏りと断定できなくても、同じ場所に繰り返し現れる場合は要注意です。
この段階で放置すると、下地や構造部まで影響が及び、修理範囲が広がることがあります。室内側のサインが見られる場合は、塗装よりも修理寄りで判断するのが安全です。
▼合わせて読みたい▼
【豊川市】雨漏り放置で野地板が腐る?屋根カバーか葺き替えかの判断基準
屋根だけで判断しない方がいい理由

屋根に劣化が見られると、原因も対策も屋根だけにあると考えがちです。
しかし、屋根は建物全体を守る要素の一部であり、単体で切り離して判断すると、後から別の問題が表面化することがあります。屋根工事を検討する段階では、視野を少し広げることが重要です。
屋根と外壁は同じ環境にさらされてきた
屋根に劣化サインが出ている場合、外壁も同じ年数だけ紫外線や雨風の影響を受けてきた可能性があります。
表に出やすい場所が違うだけで、劣化の進行度が近いケースも少なくありません。同時に対処してもらうことで、被害を「最小限に食い止める」ことを重要視しましょう。
屋根工事は外壁状態を確認する好機
屋根の塗装や修理では足場を設置することが多く、外壁の状態も同時に確認しやすくなります。屋根だけで判断すると、数年後に外壁でも同様の検討が必要になる場合があります。
単体判断が後悔につながることもある
すぐに同時工事を決める必要はありませんが、屋根をきっかけに建物全体を整理しておくことで、判断ミスや手戻りを防ぎやすくなります。
▼合わせて読みたい▼
家の外壁劣化のよくある症状!自分で修理や補修をするときの絶対NG行動
FAQ|豊川市で屋根塗装・修理を検討する際によくある質問

屋根工事は、外壁塗装以上に状態が見えにくく、不安を感じやすい分野です。ここでは、豊川市で屋根塗装・修理を検討される方から特によく寄せられる質問をもとに、判断を整理するための補足をまとめました。
Q.屋根が色あせているだけでも工事を考えた方がいいですか?
A.色あせやツヤの消失は、塗膜の保護機能が低下し始めている初期サインです。この段階ですぐに修理が必要とは限りませんが、放置すると屋根材そのものが傷みやすくなります。塗装で対応できる可能性があるかどうかを判断するためにも、状態を一度整理しておくことが重要です。
Q.雨漏りしていなければ、屋根工事はまだ不要でしょうか?
A.雨漏りは劣化の最終段階で起きることが多く、雨漏りが出てからでは修理範囲が広がる可能性があります。割れ・ズレ・棟板金の浮きなどが見られる場合は、雨漏りがなくても注意が必要です。「被害が出ていない=安心」とは限らない点を理解しておくことが大切です。
Q.塗装で済むのか、修理が必要なのかはどう判断すればいいですか?
A.判断の分かれ目は、劣化が表面だけにとどまっているかどうかです。色あせやコケであれば塗装対応が可能なケースもありますが、割れ・欠け・ズレ・固定不良がある場合は修理を前提に考える必要があります。自己判断が難しい場合は、状態確認を目的とした診断で整理するのが安全です。
カトペンと一緒に考える|豊川市で屋根工事を後悔なく判断するために

豊川市で屋根塗装や修理を検討する際に大切なのは「塗装か修理か」を急いで決めることではありません。まずは、今の屋根にどんな劣化サインが出ているのかを整理し、本当に必要な工事は何かを見極めることが、後悔を防ぐ第一歩になります。屋根の劣化は、見た目だけでは判断しにくく、気づいたときには進行しているケースも少なくありません。
その一方で、すべてがすぐに工事を必要とする状態とは限らず、
「まだ待てる」
「今は補修で十分」
という判断が成立する場合もあります。重要なのは、不安や営業トークに流されず、劣化状況を基準に冷静に考えることです。
株式会社カトペン/プロタイムズ東三河店/豊橋中央店では、工事を前提に話を進めるのではなく、屋根の状態を整理しながら「今やるべきか」「修理が必要か」「外壁も含めて考えた方がよいか」といった判断を一緒に確認していきます。判断に迷っている段階でも構いません。
問い合わせフォームからのお問い合わせ、メールでのご相談、電話でのご相談、ショールームへのご来店など、ご都合に合わせた方法でカトペンにご相談ください。豊川市で屋根塗装・修理を検討されている方が、納得した判断をできるよう、カトペンが丁寧にサポートします。
▼合わせてチェックしたい▼
1341件